保険の加入を検討する際にインターネットで調べていると保険代理店のHPやファイナンシャルプランナー(FP)が書いているブログしか出てこないと思ったことありませんか。
それは保険の紹介料が高く、どこの保険代理店、FPも検索で上位表示されるように取り組んでいるからです。
そのため、本当にお得な情報が得られにくくなっています。
本記事では築40年以上の中古戸建て物件に住んでいる私が「火災保険に加入する際に実践した方法」と「注意点」について解説していきます。
私は複数社火災保険の加入を検討してみて、6年契約で約10万円の保険料節約に成功しました。
あなたの最適な火災保険選びの参考にしてみてください。
- 企業やFPの情報ではなく加入者のリアルの声を知りたい方
- 中古戸建て物件に住んでいて、お得な火災保険に入りたい方
私の見積り結果をすぐに知りたい方はこちらクリックしてください。
火災保険の相場を知ろう
保険の比較一括サイトで火災保険相場を調べる
持ち家の場合は「建物の構造」「延床面積」「築年数」など様々な条件によって保険料が変わってきます。
その為、必要な補償は何かを把握した上で、保険料の相場はどれくらいなのかを調べる必要があります。
保険について詳しくない場合は、必要な補償内容が分からないと思うので、対面型の保険会社にも見積りをとることをおすすめします。
私も火災保険の相場を調べる際は比較サイトを利用して見積りをしてもらいました。
利用した見積り比較サイトがこちらです。
一括サイトで見積りを申し込むと契約している近くのコンサルタントもしくはファイナンシャルプランナー(FP)と面談することができます。
その際に複数社の保険会社の見積りを持ってきて頂けて、比較することができます。
私はFPの方も複数人会ってみて、言っていることが正しいのか確認したかったので2つの比較サイトを利用しました。
FPさんとの面談内容がどうだったかについてはこちらの記事に書いてあるので良かったら見てみてください。
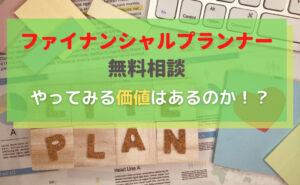
現在火災保険に加入している方は加入している保険の内容、料金と比較してみて高いのか安いのかを調べるようにしてみてください。
一度の見積り依頼では良いFPさんと出会えない可能性も高いので時間と手間を惜しまないのであれば複数人のFPさんに会うのをおすすめします。
ちなみに私は保険スクエアbang! 火災保険と【火災保険の窓口】を利用しました。
ネット火災保険も検討してみる
対面型では大手保険会社の紹介がメインとなります。
冒頭でもふれましたが、紹介料が高い会社を紹介した方が沢山の売上をあげることができる為、ネット保険のような紹介料が安い会社についてはあまり紹介して頂けません。
その為、ネット保険会社についてはネット上で簡単に見積りすることができるので、保険料を安くしたい方は比較のために是非やってみてください。
条件を揃える為に、1度対面型のコンサルタントもしくはFPさんにお会いした後にやるのをおすすめします。
ネット型の保険は必要な保障内容にカスタマイズできるので、保険料を安くするのにおすすめです。
私は「楽天損保ホームアシスト」「ソニー損保ネット火災保険」「ieho ダイレクト火災保険」「セコム安心マイホーム保険」の4社を検討してみました。
私の住んでいる家は築年数が40年以上の古い物件だった為、楽天損保は家財のみにしか保険を掛けることが出来ませんでした。
ieho ダイレクト火災保険についても1982年以降に建てられた家しか保険を申し込むこが出来ない状況でした。
古くなればなるほど申し込めなくなる可能性が高まるのでネット保険への申し込み、切り替えは早めにやるようにしてください。
ネット保険それぞれの見積りはこちらのリンクからできるので、興味のある方は試してみてください。
対面型とネット保険はどちらが良いのか
対面型の保険とネット型保険のそれぞれのメリット、デメリットはこちらになります。
- 火災保険に関する知識がなくてもお勧めされた保険に加入できる
- 加入時に色々調べる時間が取られない。(お任せで進められる)
- 火災保険の請求時に担当者に相談できる
- 保険知識の豊富な方にアドバイスをもらうことができる
- 保険料が割高
- 不必要な補償があっても外せないなどカスタマイズしにくい
- 知識がないまま特約や過剰な補償をかけてしまう可能性がある
- 保険料を安く抑えられる
- ネット上で見積りから契約まで完結できる
- 24時間申し込みを行うことができる
- 必要な補償のみにできるなど、カスタマイズ性が高い
- 対面型のように余計な特約、割高なボッタくり保険への勧誘がされない
- 自分で保険の補償内容、加入方法など調べる必要がある
- 火災保険の請求時は自分で全て行わなければならない
- 不明点があった場合はコールセンターへ相談する形になる
- 保険の審査が厳しい傾向にある
それぞれの保険のメリット、デメリット、自分にとって最適な方法での保険加入を検討するようにしてください。
火災保険の補償内容を決めよう
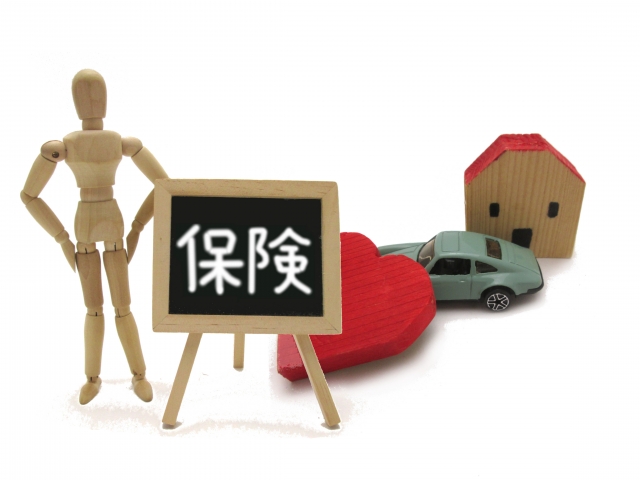
補償対象はどこまでにするか
火災保険では補償の対象を3つから選択することができます。
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財両方
建物は建物本体だけでなく、門・堀・物置・車庫まで「建物に付随して動かせないもの」を指しています。
家財は家具・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの「建物の中にあって動かせるもの」のことになります。
火災にあった際にいづれかの保険しか掛けてない場合は片方しか補償が受け取れないので、注意して選ぶようにしてください。
賃貸の場合は大家が建物に関する保険を契約する為、家財のみの補償をかけるようにしてください。
補償範囲をどこまでにするか
保険金の支払い対象となる事故の範囲をどこまでにするのかを選ぶ必要があります。
| ➀火災リスク | 火災、落雷、破裂・爆発による損害を補償 |
| ②風災リスク | 風災、雹(ひょう)災による損害を補償 |
| ③水災リスク | 床上もしくは地盤面より45cmを超える浸水などによる損害を補償 |
| ④盗難リスク | 未遂も含めて強盗や窃盗などによる損害を補償 |
| ⑤水濡れリスク | 排水管の破損による水濡れなどによる損害を補償 |
| ⑥飛来リスク | 外部から車の衝突、ボールが飛んできて建物・家財の破損などを補償 |
| ⑦破損・汚損等リスク | 日常生活で建物や家財をうっかり壊した物を補償 |
どのような災害に備える必要があるのか明確にしてから加入する必要があります。
近くに川や海がないにも関わらず、水災リスクに備える補償に加入するなど無駄がないようにしてください。
また、それらの災害がどれくらいの確率で起こり、どれぐらいの価格がかかるのかを知った上で加入すれば過剰な保険へ加入するのを防ぐことができます。
補償金額をいくらにするか
補償範囲を決めたら建物、家具に関する補償金額をいくらにするか決める必要があります。
火災やその他の損害を受けた際に元の生活を取り戻すにはいくら必要かを家族で話合って決めてください。
保険期間、保険料の払い込み方法をどうするか
保険期間によって支払うトータルの金額が変わってきます。
築年数の長い物件は1年ごとでしか契約できない場合があるなど制約が多いです。
そもそも火災保険を掛けれなくなるリスクもあるので築年数が長い物件については長期の契約をおすすめします。
新築の場合も売却や引っ越すことがないのであれば長期契約をして問題ないと思います。
賃貸の場合は引っ越す可能性も踏まえて、住むであろう年数分の期間にて契約するようにしてください。
保険料の支払い方法は一括払い、年払い、月払いと選ぶことができます。
一括払いにすればトータルで支払う金額を減らすことができますが、一回での支払う金額が大きくなります。
家庭経済状況に応じて選ぶようにしてください。
地震保険に加入するかどうか
火災保険だけでは地震が原因の火災、家の倒壊、津波による被害を補償してもらえません。これらを補償してもらう為には地震保険に加入する必要があります。
日本は非常に地震が多い国なので、地震保険に入った方が良いとFPさんからも強くおすすめされました。
地震保険は火災保険の30~50%が保険の限度額となっています。
仮に火災保険に1000万円の保険金を掛けた場合、地震保険は最大でも500万円となります。
保険料の請求時も時価が500万円以上でなければ全損でも500万円を貰うことができません。
東日本大震災の時でも全損という認定は無く、大半損(建物・家財地震保険金額60%)という認定にほとんどになっています。
注意して地震保険には加入するようにしてください。
オプションに加入するかどうか
個人賠償責任補償特約、弁護士費用特約、臨時費用補償特約、類焼損害補償特約など日常生活を取り巻くリスクへの備えとして、オプションの特約が用意されています。
保険は万が一起こった場合に立ち直れないようなリスクに備えるものと考えているので、個人賠償責任特約以外は不要と考えています。
個人賠償責任特約も自動車保険等で加入されている場合は不要です。
類焼損害補償特約の加入も検討しましたが、火事を出しても出火原因に重大な過失がない限り、火元は類焼先の損害を賠償する責任はないと法律で決められていることを知りました。
もらい火で自分の家を焼かれても火元に損害賠償を求めることが出来ないので、火災保険に加入する必要性があります。
過去の事例でも類焼損害補償特約はほとんど支払われたことがないので、こちらの特約に加入する方は少ないようです。
実際の見積り結果は
各社の見積り結果
見積りした際の条件はこちらになります。
- 築40年以上
- 戸建て
- 木造(耐火性能なし)H構造
- 地震保険割引なし
見積り結果
各保険会社の補償内容は表にまとめています。Sニー損保は個人賠償責任3億円もつけた金額になっています。
他の3社はオプション特約なしの価格となっています。
契約期間は火災保険6年、地震保険5年。一括払いにした場合の見積り金額となります。
対面型とネット型保険それぞれ希望条件に近づける形で見積りを取った結果がこちらです。
| 保険会社 補償内容 | Sニー損保 (ネット型) | T海上日動 (対面型) | Sコム損保 (対面型) | S保ジャパン (対面型) |
|---|---|---|---|---|
| ➀火災リスク | 建物1000万円 家財300万円 | 建物1000万円 家財300万円 | 建物1000万円 家財300万円 | 建物1000万円 家財300万円 |
| ②風災リスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③水災リスク | × | × | × | × |
| ④盗難リスク | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑤水濡れリスク | × | 〇 | × | 〇 |
| ⑥飛来リスク | × | 〇 | × | 〇 |
| ⑦破損・汚損リスク | × | × | × | × |
| 地震保険 | 建物0円 家財150万円 | 建物500万円 家財150万円 | 建物500万円 家財150万円 | 建物500万円 家財150万円 |
| 見積り結果 | 約8.1万円 | 約21.5万円 | 約19.2万円 | 約22.1万円 |
私が選んだ火災保険は
複数社見積りを取ったことで、相場や火災保険に入れる会社と入れない会社があることがわかりました。
補償は最低限で良いと考えていたので、ソニー損保の火災保険に加入しました。
それによって約10万円ほど火災保険料を節約できています。
疑問点については契約時に親切丁寧に電話で教えて頂けたので、対面式じゃなくても問題なく契約をすることができました。
加入時の注意点は
火災保険は築年数が古い家になればなるほど、契約できないことや保険料が割高になる傾向です。
今は契約できても1ヶ月後には契約できないという可能性もあるので、切り替えや新規契約を検討している場合は早めに行動するようにしてください。
ちなみにソニー損保は現在1980年(昭和55年)以前の物件については申し込めなくなるなど2021年4月から変更になっています。
最後に
ネット型、対面型の保険それぞれの良い点と悪い点があります。
何より一番大切なのは相場を知って、納得してから加入することです。
あなたに取って何が一番良いのか比較した上で検討した上で契約するようにしてみてください。
火災保険料を重視する方にはネット型の保険がおすすめです。
火災保険について勉強する時間が勿体ない、保険のプロにお任せしたという方には対面型がおすすめです。
対面型を検討したい方はこちらの一括比較サービスを使ってみてください。
この記事が少しでも参考になったという方は下のブログ村のボタンをポチっとして頂けると今後もブログ記事を更新していく励みになるのでよかったらよろしくお願いします。
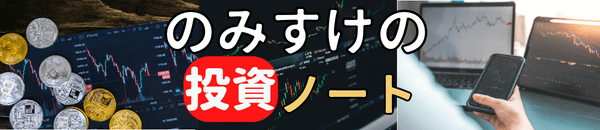


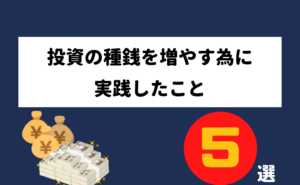
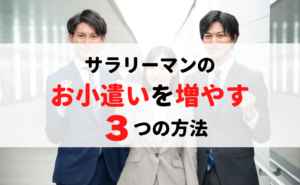

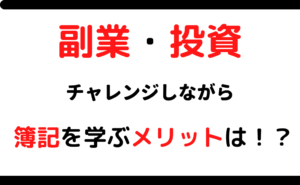
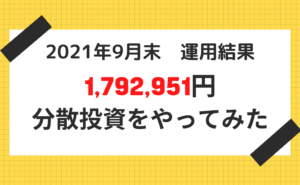
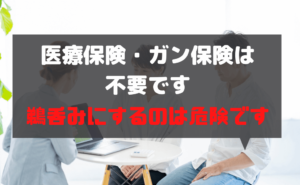
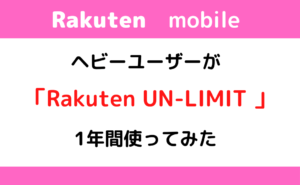
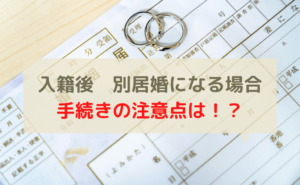
コメント